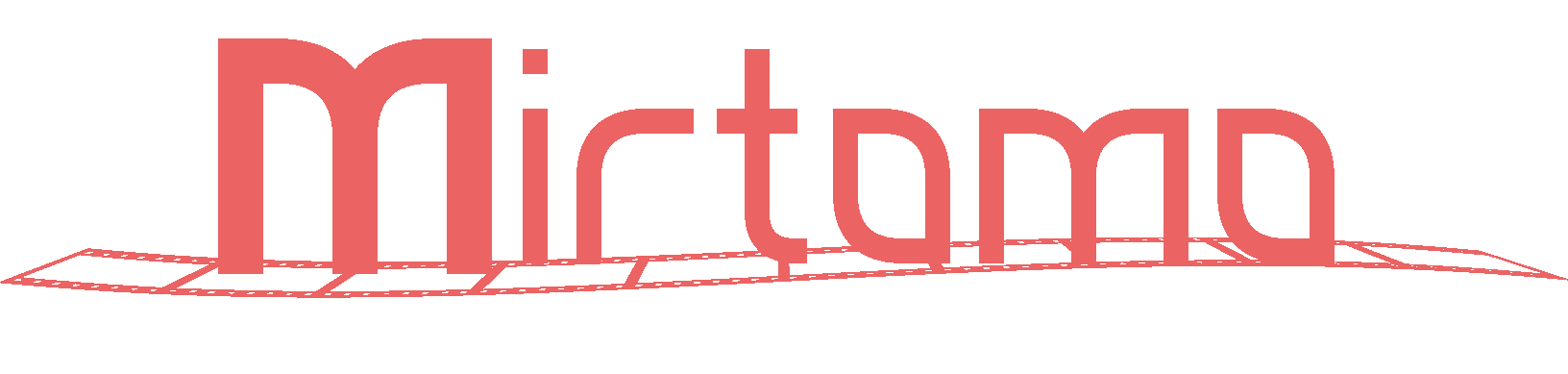『わたしは最悪。』は2022年7月1日より全国で公開されたドラマ映画です。本作で第74回カンヌ国際映画祭女優賞を受賞した主演のレナーテ・レインスヴェは本作が映画初主演。ノルウェー発、全世界から共感を呼ぶ本作の魅力を筆者の個人的な視点からご紹介します。
・人間の多面性に共感
映画の魔法に満ちた120分
映画において「尺」は大事な要素。長ければ良い、短ければ良い、という単純な話ではなく、重厚な余韻に浸る3時間の映画、楽しさがコンパクトに詰め込まれた目まぐるしい90分の映画、それぞれに魅力があります。逆に冗長だったり、明らかに描写が足りなかったり、内容に対する「尺」は重要です。
本作『わたしは最悪。』は約120分の映画。映画の冒頭で、小説のように12の章立てで構成されている旨が説明されます。章立てによって良い意味で「ぶつ切り」感があり、テンポ良くストーリーが進んでいく感覚がありつつ、全体としては120分のボリュームで心地良い余韻と充足感に満たされます。この構成の妙が本作の魅力の1つだと思いました。
また、主人公ユリヤ(レナーテ・レインスヴェ)が浮気相手のアイヴィン(ハーバート・ノードラム)に会いに行くシーンで、恋に落ちた2人以外の時間が止まったような演出は本作のハイライトの1つ。あえてデジタル効果を使わず、本物の人間がじっと立ち止まって撮影したからこそのキュートな映像美。舞台となるノルウェー・オスロの美しい景観にも要注目です。
他にもアニメーションと実写の融合を取り入れるなど鮮烈な演出がありましたが、個人的には別れ話をする2人のセリフをユリヤのナレーションとして表現するシーンが印象的でした。声を荒らげたり、悲しみを滲ませたり、そういった音声は聞き取れず、淡々としたユリヤのナレーションだけが流れます。自分が発した言葉なのに、自分に向けられた言葉なのに、なぜか他人事で上の空、という感覚が的確に再現されていて面白いです。
映画ならではの多様な表現が、特徴的な構成と完璧な密度で120分に収められた傑作です。
人間の多面性に共感
本作『わたしは最悪。』はキャッチコピーなどでも「共感」という言葉が強調されています。実際、アーティストでもなく、パーティにも縁がない筆者にもたくさんの共感ポイントがありました。なぜか。本作には「現代を生きる特定の世代の人間が共通して持っている感覚」のようなものがものすごくリアルに描かれていたからではないか、と思いました。
環境問題やジェンダー平等などの社会問題に高い関心を持っているとされるZ世代。そのZ世代にはギリギリ含まれないけど、一応まだ若いという今の30歳前後に大変「刺さる」内容だったと思うのですが、いかがでしょうか(笑)。
本作はユリヤの恋愛がストーリーの主軸ですが、たびたびセンシティブな話題が入り込んできます。性差別の描写もあるブラックジョークの漫画家、その漫画家とフェミニストの闘い、他にも過激な環境保護活動がキッカケで破局した恋人、親世代との結婚観のズレなど…。
そういった話題に対して、老年世代のように煙たがったりはせず、かといってZ世代ほど高い意識で向き合えない、あらゆる社会問題に辟易としていて、常にすべてのことに薄っすらと失望感を感じているように見えるユリヤの言動にとても共感しました。
現実に1人の人間が生きていく上では社会問題だけでなく、仕事や恋愛や向き合うべき個人的な問題がたくさんあります(「恋愛をすることが当たり前」という価値観とどう向き合うか、なども含め)。その過程には幸せも悲しみもあり、それらは人生の中で地続きに繋がっています。
前述の通り本作『わたしは最悪。』は全12章で構成されており、それぞれの章ではユリヤという1人の人間の様々な側面にスポットを当てています。だからこそ、エピローグで明かされるユリヤが選んだ道は良いか悪いかを単純に判断できるものではないし、本作が多くの人に「これは自分の物語だ」と感じさせる実在感を持った作品になっているのだと思いました。
・人生の様々な側面を描くことで多くの人が共感できる物語に