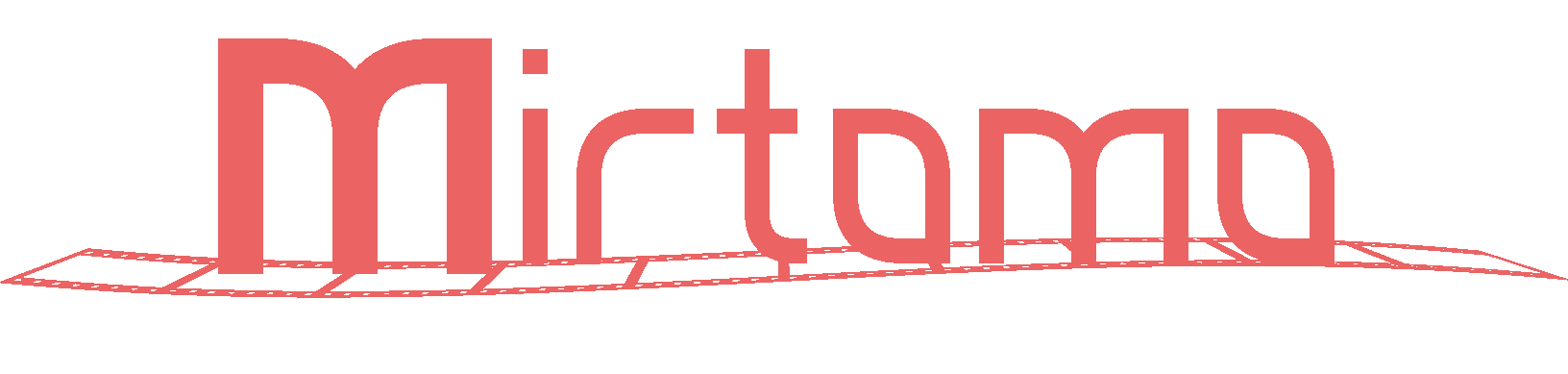一般的に昭和20年代から30年代、凡そ1950-1960年代が日本映画全盛期と言われており、1970年代は黄金時代の残り火だと個人的には思います。
今回はそれ以前の日本映画史に少し触れつつ1950-1970年代の私的日本映画傑作選を挙げてみました。
前置き 日本の映画史
映画の普及と戦前の発展
日本における初の映画上映は、鉄砲商人であった高橋信治によって1896年に行われました。
元号でいうと明治29年です。
最初の上映は発明王エジソンによる大きな箱の中を覗き穴から見るキネトスコープ方式でした。}
別の解説記事
リュミエール兄弟の発明したスクリーン上映をするシネマトグラフ方式は1897年が日本での初上映です。
こちらは実業家の稲畑勝太郎によって開催されました。
翌年(1898年)には日本における撮影技師の草分けとなった浅野四郎によって日本で初めて映画が撮影されています。
1903年には吉沢商店が浅草に日本で最初となる映画専門館「電気館」を設置しています。
浅野による『化け地蔵』『死人の蘇生』などは「映画」というより「記録映像」というべきもので、日本映画史におけるストーリーのあるフィクションの登場は『本能寺合戦』(1908)が初となります。
『本能寺合戦』を監督した牧野省三(1878-1929)は日本初の職業映画監督として日本映画史に名前を残しています。

牧野省三 出典:Wikipedia
日本におけるシネマトグラフ方式の初商業上映は前述の通り1897年ですが、ルイ・リュミエールが世界初の商業映画上映をシネマトグラフ方式で行ったのは1895年で遅れはわずかに2年です。
世界初のストーリーのある映画は『月世界旅行』(1902)と言われているので、日本映画はわずかに6年しか遅れをとっていません。
明治維新が起きて海外から大量に情報が流入したとはいえ、物流も情報伝達速度も今と比べ物にならないぐらい遅かったはずです。
それでこれほど早い段階で映画の興行が行われていたことに調べていて筆者も驚きました。
その後、日本映画は凄まじい勢いで進化していきます。
1910年代になると日活などの映画会社が設立され、撮影所も設けられます。
この頃はまだサイレント映画だったため、映画に解説を加える日本独自の文化「活動弁士」(1930年代末ごろにほぼ消滅)も誕生しています。
1920年代から1930年代になると、小津安二郎(1903-1963)、溝口健二(1898‐1956)、内田吐夢(1898-1970)など戦後も活躍する映画監督がデビュー。

小津安二郎 出典:Wikipedia
1920年代にサイレントからトーキー(音のある映画)に移行して、技術面が進化。
アメリカでも演劇から映画に人材が流入したように、日本では歌舞伎などの伝統芸能や新劇から人材が流入し、内容面でも充実していきます。
時代劇のスター俳優たちが競って個人プロダクションを興し、野心満々の若い映画監督や脚本家を呼び寄せて彼らに機会を与えます。
これらの個人プロダクションがトーキーの波に対応できずに消滅すると、人材が大手映画会社に移り活躍しました。
1941年以前、日本はアメリカに次ぐ年間500本(!)近い映画を制作していました。
ところが……です。
皆様ご想像の通り、ここで歴史的な大事件が起きてしまいます。
第二次世界大戦(1939‐1945)です。
1941年に主戦場はヨーロッパから太平洋戦線により、日本は本国の国土にも多大な被害を受けました。
ABCD包囲網による経済制裁でアメリカからのフィルム輸入が途絶え、国産フィルムは軍需品とされ、厳しい使用制限がかけられました。
終戦した1945年。その年の日本映画製作本数は僅か26本でした。
ただし、戦中は日本映画界にとって暗いニュースだけだったわけではありません。
戦争真っただ中に後に世界的巨匠となる黒澤明(1910-1998)が『姿三四郎』(1943)で監督デビューを果たしています。
戦後の隆盛
戦後、GHQによる間接統治が行われ、日本で製作される映画はGHQの下部組織CIE(民間情報教育局)によって管理されることになりました。
谷口千吉・監督、黒澤明・脚本の『暁の脱走』(1950年)は当初、山口淑子(満映の李香蘭)主演の朝鮮人従軍慰安婦を描いた作品としていましたが、数十回に及ぶCIEの検閲により、原形を留めない作品となってしまっています。
ですが、この検閲時代は長くありませんでした。
1951年にサンフランシスコ講和条約が締結されると、翌年にGHQによる映画検閲が廃止となります。
これにより上映禁止となっていた時代劇が復活するとともに、多数の映画が製作されるようになりました。
日本映画の国際的評価も上昇し、1951年に黒澤明が『羅生門』でヴェネツィア国際映画祭グランプリを受賞しています。

出典:IMDB
この時代の日本映画生産システムは、スタジオシステムです。
要は大手の映画会社が制作から配給、上映までは寡占するスタイルの事だと思ってくれればいいです。
日本の場合は小規模な独立プロもかなり健闘していたのですが、その辺は割愛します。
一つ挙げておくなら数々の国際的な賞を獲得した『砂の女』(1964)は当時の独立プロが生んだ傑作の一本ですね。
1953年には大手映画会社5社(松竹、東宝、大映、新東宝、東映)が専属監督・俳優らに関する協定、「五社協定」に調印しています。
後に日活が加わり、新東宝が倒産するまでの3年間は六社協定となっていました。
1960年に日本映画界は史上最高の製作本数となる547本を製作し、ピークを迎えました。
そのほとんどは大手6社によるプログラムピクチャー※でした。
しかし、この年以降、日本の映画産業に翳りが見え隠れするようになります。
観客動員数もこれより先、1958年の11億人強を最高に、急激に下降していきます。
(原因はテレビとの競争の激化)
※プログラムピクチャー=一言で括れない用語ですが、1950-1970年代の日本映画量産体制下では、二本立てのメインではなくむしろ添え物として作られた作品のことを一応指します。
1970年代になると、映画会社の業績不振からお抱えの俳優を大量解雇し、五社協定は自然消滅。
1980年代になると従来のスタジオシステムは崩壊し、大手が大作映画を全国の専属劇場で同時公開するという方式が成りたなくなります。
1961年には大手6社で520本もの映画を制作していましたが、1986年には3社で24本にまで落ち込んでいました。
かつて撮影所には映画会社と社員契約したスタッフが現場で腕を磨く「人員養成」としての機能がありました。
それが、スタジオシステムの崩壊=撮影所の解体により現場での「技術継承」が支障をきたすようになります。
『座頭市』(1989)では、殺陣のリハーサル中に真剣が刺さって死者が出るという痛ましい事件が起きています。
これは助監督が時代劇の経験がない急遽集められたスタッフであったため、進行・リスク管理に問題があったのが原因と言われています。
この事件は1980年代における技術水準の低下を物語る出来事といえるでしょう。

出典:IMDB
こうして1980年代に日本映画黄金期は質・量の両面で完全に終わりを告げることになります。
黄金時代名作映画の特徴
完全に私見ですが、黄金期の日本映画の名作は隅から隅まで作り手の意図が浸透しきっているように思います。
これもまた私見ですが、その理由は監督(少なくとも大物の)に与えられた裁量が「独裁的」と言っていいほど大きかったからではないでしょうか。
黒澤監督による日本映画の金字塔『七人の侍』は当初の予算を撮影3分の一程度の段階で使い切ってしまい、最終的に当時の平均的な日本映画の7倍にあたる巨費が投じられています。
ほか、クロサワは理想の画のために人が住んでる民家の屋根を壊した、撮影のために本物の矢を射ったなど無茶苦茶な逸話に事欠かない人です。
野村芳太郎監督は出世作になった『張込み』(1958)で、こだわりまくったせいで撮影がありえないほど長引き、7か月もかけて撮影を行いました。(当時通常の撮影期間は一か月)
野村監督は再三にわたって「帰ってこい」と映画会社から電報で催促されたにも関わらず、無視して撮影を続行したそうです。
無茶苦茶が許されたクロサワは「天皇」と呼ばれていましたが、今の日本の映画監督にここまでの裁量はおそらく無いでしょう。(ごく少数いるかもしれないですが)
それが許されたのがギリギリ1970年代までだと思います。
そんなわけで、これから挙げるのは無茶苦茶が許された時代の「遺産」です。
これらのような日本映画が作られることはおそらく、二度とないでしょう。
日本映画黄金期の傑作
『七人の侍』(1954)

出典:IMDB
最初に言っておきますが、黒澤明監督作はこの一本しか挙げません。
なぜならこの企画を素直にやるとクロサワ作品ばっかりになってしまうからです。
人情ものの『生きる』(1952)、文学的な『羅生門』(1950)、文学的でありながらスペクタクルな『蜘蛛巣城』(1957)、痛快な『用心棒』(1961)などこの時代の代表作を挙げていくとキリがありません。
その中から一本選ぶなら、やはり『七人の侍』でしょう。
本作は「野武士に襲撃されて困り果てた農民が、食いつぶれた侍たちを雇って野武士と戦う」という超シンプルな筋立てを207分もかけて描いていますが、導入から結末まで冗漫なところも余分なところもひとつもありません。
当時のハリウッド大作がダラダラ冗漫な画を繰り返す退屈な演出に終始していたのに対して、『七人の侍』は映像テクニックの塊のような映画で、プロデューサーの言いなりになった雇われ監督では決してできない大胆な表現の連続です。
基本的な作りは娯楽なので最初にクロサワ映画をみるなら、やはりまずは本作でしょう。
また、あまり語られることがない要素ですが、『七人の侍』は時代考証を徹底したリアルな時代劇の先駆者でもあります。
例えば、クライマックスの雨中の決戦で菊千代(三船敏郎)が「この刀じゃ5人と切れん」と何本も予備の刀を用意している描写があります。
日本刀は切れ味に性能を全振りした日本の変態鍛冶技術が生んだ傑作ですが、切れ味に性能を全振りしているため「折れやすい」という欠点があります。
実際、以後の時代劇、例えば後に挙げる『切腹』では狙って相手の刀を叩き折るという描写が見られます。
こんなことは私のような小物がわざわざいうことでもないですが、『七人の侍』は日本映画史どころか、映画史に残る傑作なので映画好きな方なら教養として一度は見ておいていただきたいです。
『東京物語』(1953)

出典:IMDB
クロサワはスペクタクルな時代劇のイメージが強かった人ですが、現代劇も小規模なドラマをやらせても超一級品の映画監督でした。
対して小津安二郎は「僕は豆腐屋だからね」と一貫して同じような映画を撮り続けた人です。
編集は歯切れよく、画面にはダイナミックな動きのあるクロサワに対して小津は「ないない尽くし(パンなし、ティルトなし、フォローなし、クレーンなし)」と言われるほど、ダイナミックさと無縁の映画監督です。
加えて小津監督の映画は小規模な家族劇が多く、内容も雰囲気も非常に似通っています。
はっきりいって普通の意味で感想をいうと「退屈」で、筆者も今まで何本か小津映画を見ていずれも欠伸をこらえられませんでした。
ですが、見ている間は退屈で仕方ないのに、見終わると不思議と「ああ、見てよかった」と思わさせられる映画監督でもあります。
小津監督の作品はいづれも似通った雰囲気、似通った内容ですが、一本挙げるなら『東京物語』でしょう。
尾道から上京してきた老夫婦が、血のつながった子供たちに邪険にされるのに、血のつながらない義娘には親切にされる、ただそれだけの話で、何もエキサイティングな要素はありません。
なのに見終わるとしんみりし、見てよかったと思わさせられてしまう、小津の魅力、らしさがたっぷり詰まった一本です。
『雨月物語』(1953)

出典:雨月物語公式ページ
上田秋成(1734‐1809)の読本『雨月物語』を原作にした幽玄な芸術映画です。
内容は一言で言ってしまうとホラーなのですが、ドロドロした情感がいかにも日本的で、「怖い」というより「悲しい」というべき情緒あふれる傑作です。
監督の溝口健二は戦前から活躍していた人ですが、戦後になって国際的な評価を高めました。
ワンシーン・ワンカットを多用するのが特徴的で、水墨画調の絵巻物でも見ているような流麗さが素晴らしいです。
本作はヴェネチア国際映画祭の銀獅子賞を獲得しています。
『ゴジラ』(1954)

出典:U-NEXT
言わずと知れた超人気シリーズの元祖です。
戦後間もない時期の映画なので、さすがに特撮技術は今見ると古臭いですが、ミニチュアの精度やアニメーション合成など、当時の人からしたら度肝を抜かれるレベルだったことでしょう。
いままで様々なシリーズ作品を見てきた方は意外に思うかもしれませんが、初代『ゴジラ』に光の巨人は出てこないし、モスラもキングギドラも出てきません。
ゴジラを倒すのは人間の力で、テイストとしては(今の感覚で言うと)『ゴジラ』より『ウルトラQ』に近いです。怪獣映画にしては地味な作りで、大人の観客を狙ってつくったことがうかがえます。
『シン・ゴジラ』(2016)は21世紀バージョンの原点回帰と言えますね。
(そういえば筆者が劇場で『シン・ゴジラ』を見た時、劇場で「ねえーつまんない」とぐずっている子供がいました)
\\『ゴジラ』を見るならここ!!//『二十四の瞳』(1954)

出典:IMDB
何度も映像化されている壺井栄の同名小説の最初の映像化作品です。
監督の木下惠介(1912-1998)は本作で国際的な評価を獲得することになります。
心優しい女性教師を主人公に、戦前から戦後間もない激動の時期を舞台にした本作はドロドロベタベタのウェットな感動作です。
筆者はこういう内容のものが苦手なのですが、木下監督は引き画を主体にしたドライな演出に終始しており本作には押しつけがましさが一切ありません。
木下監督について黒澤明は「僕みたいなセンチな人間がセンチな映画を撮ったらメロメロになってしまう。クールな木下くんが撮るからちょうどよくなるんだ」と語っていたそうですが、これは本作の美点を端的に表していると思います。
木下はウェットな感動作の一方、姥捨て山伝説を描いた『楢山節考』(1958)など硬派な作品でも高く評価された人です。きっとそういう芸風がちょうどいい具合のウェットさを産み出していたのでしょう。
『切腹』(1962)

出典:IMDB
武家社会のリアルと武士道の残酷性を描いたリアル志向時代劇の傑作です。
小林正樹(1916‐1996)監督は現代劇の社会派作品を得意としてた人ですが、本作以降は時代劇が続くことになります。
小林監督の演出は芸術的、時間軸を入れ替えた橋本忍の脚本も見事な構成です。
和楽器を大胆に取り入れた武満徹の音楽も情感たっぷりです。
『怪談』(1965)『上意討ち 拝領妻始末』(1967)と小林監督は続けて時代劇を撮ることになりますが、いずれ劣らぬ傑作なので本作が気に入ったならば是非どうぞ。
『飢餓海峡』(1965)

(C)東映
時代劇をメインフィールドにしていた内田吐夢監督が撮った現代サスペンスの傑作です。
貧困による忌まわしい過去を消し去るために殺人を働いてしまう社会派サスペンスで、日本らしいジメジメした情感をドキュメンタリー的な生々しさで画面に定着させています。
こういう切実な貧しさが当時の日本では切実な問題だったのでしょうね。
1960年代当時に作られた和製現代サスペンスでは『天国と地獄』(1963)と並ぶ大傑作と言っていいでしょう。
『白い巨塔』(1966)

出典:IMDB
何度も映像化されている社会派医療小説の最初の映像化作品です。
山本薩夫(1910-1983)監督は社会派ドラマを得意とした人で、当時としてはこれ以上ない人選と言えるでしょう。
この人は細かくカットを割る人でしたが、後述の岡本喜八が同じ細かく割るでもすばしっこさを感じさせたの対し、どっしり感を感じさせます。
『白い巨塔』は昭和日本の作品ですので、現代に舞台を変えるとどうしても出てしまう違和感が、同時代に制作されたことで消えているのもいいですね。
『日本のいちばん長い日』(1967)

出典:IMDB
多作だった岡本喜八(1924‐2005)の数ある代表作の一本。
本作を選んだのはただの好みです。
ポツダム宣言受諾(1945)を知らせる玉音放送までの24時間を描いた戦闘シーンの一切ない地味な戦争映画です。
セリフも登場人物も非常に多く、会話だらけですが本作は少しも退屈させられません。
岡本監督は細切れにしたカットを絶妙な感覚でつなぎ合わせていくテクニシャンで、歯切れ・テンポの良さは現代のポール・グリーングラスを思わせます。
岡本監督は晩年に至るまで、このすばしっこいスタイルを貫く通しており、だいぶ後の時代に撮られた『大誘拐 RAINBOW KIDS』(1991)はコメディで、そのすばっしこい至芸が味わえるとても楽しい映画です。
『仁義なき戦い』(1973)

出典:IMDB
ご存じ長寿シリーズの第一作目、ヤクザ映画の金字塔です。
深作欣二(1930-2003)監督は芸風の幅が非常に広い人でしたが、やはり一番イメージが強いのは本作をはじめとしたバイオレンス映画でしょう。
この人のすごいところは最晩年に至るまで、バイオレンス描写が衰えなかったことです。
結果的に『バトル・ロワイアル』(2000)が遺作となりましたが、同作は70代に突入した老人が撮ったとは思えないような先鋭的な内容です。
一作目の『仁義なき戦い』ではもっと荒々しい原始的な魅力を味わうことができます。
\\『仁義なき戦い』を見るならここ!!//
『サンダカン八番娼館 望郷』(1974)

出典:IMDB
東南アジアに娼婦として売られた「からゆきさん」に題材を取った社会派歴史映画です。
熊井啓(1930-2007)監督は骨太なスタイルで知られた名匠で1960年代から2000年代の初頭まで活躍しました。
スタジオシステムのもとバリバリの現場叩き上げでキャリアを築いた監督にほぼ共通することですが、この人もカメラワークがダイナミックなのにずっしりと安定感があり、編集は歯切れの良くスケールの大きさを感じさせる映画監督でした。
『忍ぶ川』(1972)のようなしっとりした文芸映画でも見事な手腕を見せましたが、やはり最高なのは社会派サスペンスで、21世紀の映画でもっとモダンな『日本の黒い夏─冤罪』(2001)も熊井監督の至芸をとことんなまでに味わえる逸品です。
『砂の器』(1974)

(C)1974-2005 松竹株式会社/橋本プロダクション
野村芳太郎(1919-2005)監督は娯楽色の強い作品、とりわけサスペンスを得意とした職人的な名匠です。
とりわけ、原作・松本清張、脚本・橋本忍、野村監督の黄金トリオによるサスペンスはどれも一級品のエンターテイメントで尚且つ昭和日本のドロドロした情感を味わえる傑作です。
このトリオによる作品はいくつかありますが、一本挙げるなら間違いなく『砂の器』でしょう。
移動撮影とズーミングをバンバン使った超絶技巧、かつ特大のスケールで、原作では数行で処理されていた犯人の過去の回想は完全に原作を超えています。
日本の夏の湿気を帯びた不快な暑さを画面に定着させているのも情感たっぷりです。
職人的な分野に活躍が限られたせいか、国際的な賞とはほとんど無縁でしたが、このトリオによるサスペンスは今見てもエキサイティングな一級品の娯楽映画です。
\\『砂の器』を見るならここ!!//
『犬神家の一族』(1976)

出典:IMDB
1970年代を代表する大ヒットシリーズ「金田一耕助シリーズ」の第一弾です。
監督は超多作なことで知られる市川崑(1915-2008)監督です。
市川監督は超絶技巧の持ち主で、ドキュメンタリーの『東京オリンピック』(1965)も単なる記録映像とは呼べないような濃厚な味付けがされています。
1970年代は日本の映画産業が斜陽に入った時期ですが、映画会社が苦戦する一方で角川書店の角川春樹が映画製作に進出し、豊富な予算による制作とメディアミックスによる戦略化された宣伝を展開。
本作を初め封切り公開された作品は立て続けに大ヒットしました。
当時、キャリアが低迷していた横溝正史は人気作家になりました。
それにしてもこんなドロドロした情感の土俗的な映画がヒットするのだから、結局、何がヒットするかなんて誰にもわからなってことですね。
以後、学術書を中心に扱う中小出版社だった角川は産業を多角化させ大手へと成長していくことになります。
なお、市川監督はセルフリメイクの非常に多い人でしたが、本作も2006年にセルフリメイクされています。
最終的に単独の監督作品は同作が遺作となりました。
他、市川監督の代表作として『ビルマの竪琴』(1956)もお勧めです。
同作も1985年にセルフリメイクされています。
まとめ
以上、いかがでしたでしょうか?
古い映画を観るのはちょっと身構えますが、ここの挙げた作品はいずれも日本映画史に残る傑作です。
画質、音質はさすがに現代の映画のように行きませんが、おそらく二度と作れないような映画ばかりで「遺産」として受け継いでいくべきものだと思います。
なお、すごく古い映画は録音が悪いので、字幕機能がついてるなら字幕付きでの鑑賞をお勧めします。
筆者は『七人の侍』を観るときはいつも字幕付きで観ています。